
知育とは? 0歳~5歳の子供におすすめな知育教育を年齢別に紹介!
目次
知育ってどういう意味なの?

「知育」とは自分で考える力を育てる教育です。知育と聞くと専門的な教育を思い浮かべる人もいるでしょうが、実は少し違います。知育とは計算や読み書きなどの「学習能力」のことではなく、思考力や判断力、発想力といった「知的能力」を育てることを言います。知育教育での「考える力」とは自分の置かれた状況を分析し過去の経験と照らし合わせ、適切な選択をしていくことです。「考える力」は「自分が嫌だと思うことは他人にもしない」思いやりの心に繋がるものであり、「自分はこう思うからこうする」力を身につけるなど、子供が自分の意思で行動できる人間になるために必要な要素です。
子供の知育は何歳から始める? いつまで続ければいい?

知育は0歳児から始まっています。子供は日々いろいろなことができるようになりますね。赤ちゃんの脳は産まれた瞬間からどんどん成長を続けており、0歳児からでもできる知育教育はたくさんあります。
知育教育を続ける期間について、多くの知育教育に関する書籍に乳幼児期に対する知育方法が載ってはいるものの、具体的にいつまでという期限は記載されていません。「考える力を育てる」ことが知育なので、そこに終わりはないのでしょう。この記事では、子供が家庭で過ごす時間が多い就学前の0歳~5歳児を対象とし、「知育教育」について具体的に解説します。
知育はどのように進めるといい?
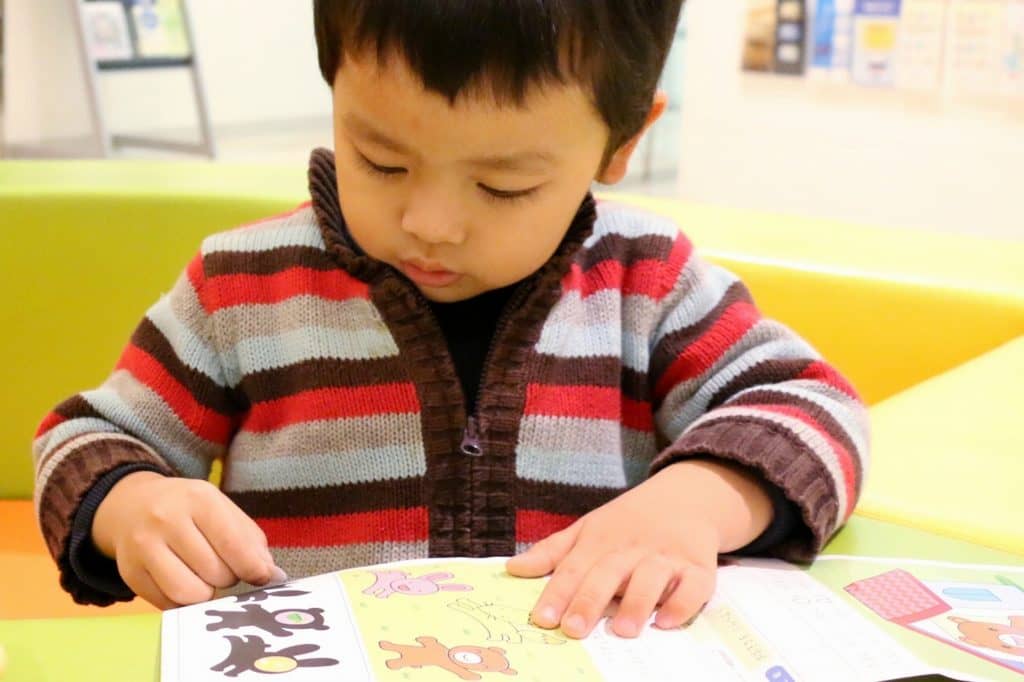
知育教育の実践方法については
- 知育玩具などの専用アイテム・アプリを購入する
- 日常生活で工夫して知育教育を行う
- 知育教育を実践している教室に通う
の3つが主流となっています。それぞれ詳しく説明します。
知育玩具や知育アプリ、知育菓子は絶対に必要?
知育玩具や知育アプリがないと知育教育ができないことはありません。ただ、専用に作られた知育玩具や知育アプリは、小児科医が監修していたり、世界の知育方法を取り入れていたりとさまざまなアイデアが詰まっています。大人も一緒に遊べるようなクオリティの高い知育玩具やアプリもたくさんあり、子供と一緒に遊んでみるのもいいでしょう。知育菓子は「食べると賢くなる」のでなく、「食べるまでの過程に楽しい作業があり知育効果が期待できる」物です。いつものおやつの代わりに知育菓子を取り入れて、食べるまでの作業を楽しむのもいいでしょう。
知育玩具では木のパズルや音の出る本、ブロックなどの人気が高く、知育アプリでは人気キャラクターのクッキングゲームや電車ゲームなど、好奇心をくすぐりながら考える力が養えるタイプが人気です。
【タッチ!あそベビー 赤ちゃんが喜ぶ子供向けのアプリ】
0歳~3歳向けのアプリです。画面をタッチすると色や形が変わり、ごはん・着替え・電車・お店屋さんなど身近な物でごっこ遊びできます。アプリを起動してワンタッチで始められるので、赤ちゃんがぐずった時などもサッと使えて便利です。
家庭でも工夫すれば知育教育は実践できる?
知育玩具やアプリを購入しなくても家庭で知育教育を行えます。例えば指先を使った遊びは知育に効果的だとされ、折り紙や紐通し、豆運びなど、家庭にあるものを使って実践できる物も多くあります。
また、想像力を働かせる遊びとして「ごっこ遊び」も知育に効果的です。自分をパパママなど誰かに見立てたり、ぬいぐるみを生きてるかのように喋らせたりすることは子供によくある風景のため見逃してしまいがちですが、実はとても効果的な知育教育です。
絵本の読み聞かせや言葉遊びも知育にいいとされます。「逆さ言葉遊び」や「お話作り」など、自分で考えながら話す行為は子供の脳に刺激を与え成長を促してくれます。
知育教室に子供を通わせるのはどう?
知育教室では月齢に合わせ、効果的な教材を使って適切な教育を行ってくれます。一般的に0歳~小学校6年生までが知育教室の対象とされており、0歳~2歳までは親子で参加する知育教室が多くあります。
筆者も子供が生後半年くらいの時に、体験で知育教室に参加しました。筆者が感じた知育教室のメリットは、子供が行動した際に「親が見守るべきなのか、褒めるべきなのか、助けていいのかなど、どのような対応を取ればいいか」を知育の観点から先生が指導してくれることです。これらの行動1つ1つが子供の成長を左右するのだと思うと慎重になりそうだと感じました。そういう意味で知育教育のプロにサポートしてもらえるというのは非常に心強かったです。知育教室の利用にはある程度の月謝もかかり、知育教室によってプログラム内容も異なるため、興味がある人は近くの知育教室についてホームページなどで詳しく調べてみてください。
年齢別の知育教育の進め方【0歳~1歳】

知育には成長過程に合わせた適切な教育方法があります。どのタイミングでどんなことを子供に体験させてあげるといいのか、年齢別に解説します。
0歳~1歳では五感を刺激して脳を成長させましょう。この時期の赤ちゃんはまだ言葉も話せず自由に動けませんが、その間も脳はどんどん成長します。0歳~1歳の赤ちゃんは「見る」「聞く」「触る」感覚を通じて脳に刺激が伝わり、成長が促されます。また「これはなんだろう?」と興味を抱かせることも大切です。
カラフルなモビール・メリー

産まれてすぐの赤ちゃんにおすすめなのがモビールやメリーです。0歳~1歳の赤ちゃんは物をじっと見つめたり、動く物を目で追いかけたりして視覚から刺激を多く受ける時期です。モビールやメリーには優しい色合いの物もたくさんありますが、生まれたばかりの赤ちゃんは曖昧な色合いを識別しづらいためコントラストが強い色のアイテムがおすすめです。
モビール:糸などで薄い造形物を吊るした物でインテリアでよく見かけます
【モビール・メリーおすすめ1:Gollnest&Kiesel(ゴルネスト&キーゼル)モビール エレファント】
かわいらしいゾウが8頭ついたモビールです。カラフルで赤ちゃんも認識しやすく、ベビーベッドなどの上につけてあげると目で追う仕草が見られるでしょう。ゾウの耳と胴体の組み合わせを自由に変えられます。
【モビール・メリーおすすめ2:ディズニー Dear Little Hands ふんわりミニメリー くまのプーさん】
プーさんや仲間たちがついたメリーです。クリップでベビーカーやバウンサーなどに取りつけて使えます。ベビーカーの振動や風でプーさんたちがゆらゆら揺れて赤ちゃんも喜んでくれるでしょう。3体のキャラクターがついている位置の違いから、遠近感覚のトレーニングにもなります。
絵本の読み聞かせ

赤ちゃんは言葉を話し始める前の時期でもたくさん言葉を聞いて吸収します。絵本を読み聞かせるとパパママの声に耳を傾けたり、絵柄を不思議そうに見つめたり、手を伸ばして絵本を触ってみたりと、赤ちゃんなりに興味を示すでしょう。絵本の読み聞かせはいろいろな知育教育効果が期待できます。
【絵本おすすめ1:もこ もこもこ】
しーんとした場面から突然地面がもこっと盛り上がり、もこもこっと膨れ上がり、最後には…? 不思議で愉快な世界にいつの間にか親子揃って引き込まれます。「もこ」「にょき」「ぽろり」など擬音も楽しめます。
【絵本おすすめ2:じゃあじゃあびりびり】
水はじゃあじゃあ、イヌはわんわん、紙はびりびりびりと1ページに1つの音が登場します。文字の配置も工夫されていてまるで本当に水が出たり、紙が破けたりしているようです。メリハリのある色彩で赤ちゃんにもわかりやすく、赤ちゃんの最初の本として長年親しまれています。
積み木遊び
積み木を触ったり、投げたり、積み木同士を合わせてカチカチさせたりと、積み木の感触や音も赤ちゃんに刺激になります。積み木を口に入れて「固い」と感覚を知ったり、食べ物ではないと学んだりできるなど積み木は知育に非常に役立ちます。赤ちゃんが何でも口に入れてしまう時期には誤って飲み込まないような大きさを選び、口に入れても安全な製品であるか確認しましょう。
【積み木おすすめ1:べビラボ やさしいやわらかつみき(アンパンマン)】
研究に基づいた赤ちゃんにわかりやすい柄を各ピースに採用しています。柔らかい素材で10ピース入っており、パリパリした音や鈴の音も楽しめます。初めての積み木におすすめです。
【積み木おすすめ2:エド・インター デザインつみき】
カラフルな物や中にビーズが入った物など、13種類41ピースが入っています。赤ちゃんが誤飲しにくい大きめサイズで、口に入れても安全な塗料を使っています。収納用の台車にはガイドとなるイラストがあるので、パズル感覚でお片づけできます。
動かすおもちゃ

赤ちゃんが1人でお座り・ハイハイできるようになったら、目の前に動くおもちゃを置いてみましょう。赤ちゃんが興味を持って体を動かしたり、「触ると動く」新しい体験ができたりなど刺激がいっぱいです。音が鳴るボタンがあったり、動くとカタカタと音がしたりといろいろな仕掛けがついたものもあるので、子供の興味に合わせて選んでください。
【動かすおもちゃおすすめ1:BRIO (ブリオ) プルトイ キリン】
高さ約20cmのキリンのおもちゃで、紐を引くと首をゆらゆら揺らしながら動きます。歩き始める前でも手で動かして楽しめます。ヨーロッパの基準よりさらに高い基準で独自の安全試験を行い、材料の木材はFSC森林管理認証を受けています。
【動かすおもちゃおすすめ2:まわしてクルクルサウンド】
3種類のパーツをくるくる回すと音が出たり、中のビーズが跳ね回ったり、横の星が光ったりと楽しい仕掛けが満載です。下の人形を押すと「ボヨーン」と愉快な音が鳴り人形が下がります。赤ちゃんの好奇心を促します。
次のページでは2~5歳ころの知育教育の進め方を解説!

















